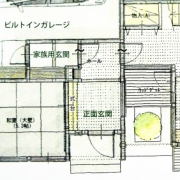【OOSHITA’s BLOG】
脱線記事です。
しかもおじさんくさいです。

先日、ひさびさの休みで、「美濃の正倉院」こと横蔵寺(揖斐川町谷汲)に行ってきました。
多くの重要文化財があり、
紅葉の名所でもあり、
即身仏(ミイラ)が安置されていることでも有名なこのお寺。
しかし恥ずかしながら私はこれまで行ったことがなく、嫁の案内で初めて行きました。
片道45分。
車内で子供を寝かせるには良い距離です。
着いてみると…

雰囲気のある場所でした。
不揃いの石段、何百年も風雨に晒された木の表情、そして見事な紅葉。
歴史ある古い寺がちゃんと残ってる、という感じ。
即身仏の安置場所を示す張り紙におもいっきり
「← ミイラ」
とか書かれちゃってるのは、まぁご愛嬌…(笑)

こういう古い場所を良いなぁと思うようになったのは、私がおじさんになったからでしょうか。
だとしたら、おじさんになってよかった。
紅葉も、いちばん良い時期とは少しズレていたと思いますが、それでも綺麗でした!
紅葉といえば、ウチに植えたモミジも色づいてきました。
茶色っぽい色になってるので、理想とするような真っ赤な色には今年はならなさそうですが…
肥料のあげ方とかで、紅葉のしかたは変わるそうですね。
せっかくのモミジなので、なるべく綺麗に紅葉させるよう、来年からちょっと研究してみたいと思います。

そして週末には土岐市まで遠征し、食器を買ってきました。
土岐市や多治見市といえば、全国でも有数の陶器の産地。
普段使いのお皿から人間国宝作の芸術作品まで、「美濃焼」を見たければやはりこの地域です。
美濃焼は、その製法によって「志野」「織部」「黄瀬戸」などに分かれるのですが、私が好きなのは志野。

紅い土に砂糖をかけたような独特の温かみが特徴です。
特に湯呑みやぐい呑みは志野が一番!と個人的に思っており、おめでたいことがあった日などには愛用の器を出してきて使っております。
今回行ったのは土岐市の「道の駅 志野・織部」。
目当ては普段使いの器です。
魚が載るような長めのやつと、お客さん用の茶碗。
この道の駅だけでもかなり多くの器を置いていますし、そこから階段を上がれば、器を扱う多くのお店や作家さんの工房などが並んだ窯業団地みたいになっています。
それこそ1枚百円くらいの物から、ショーケースに展示された値段表示のない物まで、充実のラインナップです。
行ってみて思い出したのですが、
何年か前にここに行った時、
ものすごくカッコいいぐい呑みを見つけて興奮してるところを、その作家さんご本人に偶然見られていたことがありました。
そのぐい呑は、作家さんのご厚意により、申し訳ないくらいのお得な値段で譲っていただきました。

作品を格安で私に売ることになり損をしたであろう作家さんですが、嬉しそうに、かつ不器用そうに
「ありがとう。嬉しいね。ありがとう」
と繰り返しながら器を包んでくださったのが忘れられません。
60歳を過ぎた陶芸家の先生でさえ、自分の作品を人に理解され、気に入られるとやっぱり嬉しいんですね。
名も知らぬ若造に作品を褒められただけでも。
家も、たくさんの職人さんの手によって作られます。
設計する人、色や材質を決める人、地盤を固める人、基礎を作る人、家を作り上げる大工さん、断熱材の施工業者さん、左官の職人さん、クロスの職人さん、建具の業者さん、電気工事の人、水道屋さん、外構の業者さん…
さらに、建築現場に直接来ないまでも、家に入る色々な製品を開発し、製作している人たちもいるわけで。

その全てに思いを馳せていたら大変ですし、職人さん全員とお話しするような機会はもちろんありません。
でもやっぱり、「いい仕事をしていただいた」と感じたならば、素直にその気持ちを職人さんに伝えられると喜んでもらえますし、時間があるならば専門分野の話を聞くと面白いです。
そういう職人さんとの触れ合いも、家づくりの醍醐味の一部だと思います。
見方を変えれば、
職人さんの仕事に対してお礼を言いたいくらいの気持ちで家づくりを終えられたなら、施主としてもすごく幸せなことだな、と。
そう思います。





![[WEB内覧会]LDK](https://www.mori-juken.jp/smilest/wp/wp-content/themes/wp_temp2/timthumb/timthumb.php?src=/smilest/media/51/20171015144222.jpg&h=180&w=180&zc=1&q=100&a=c)